第1問(難)
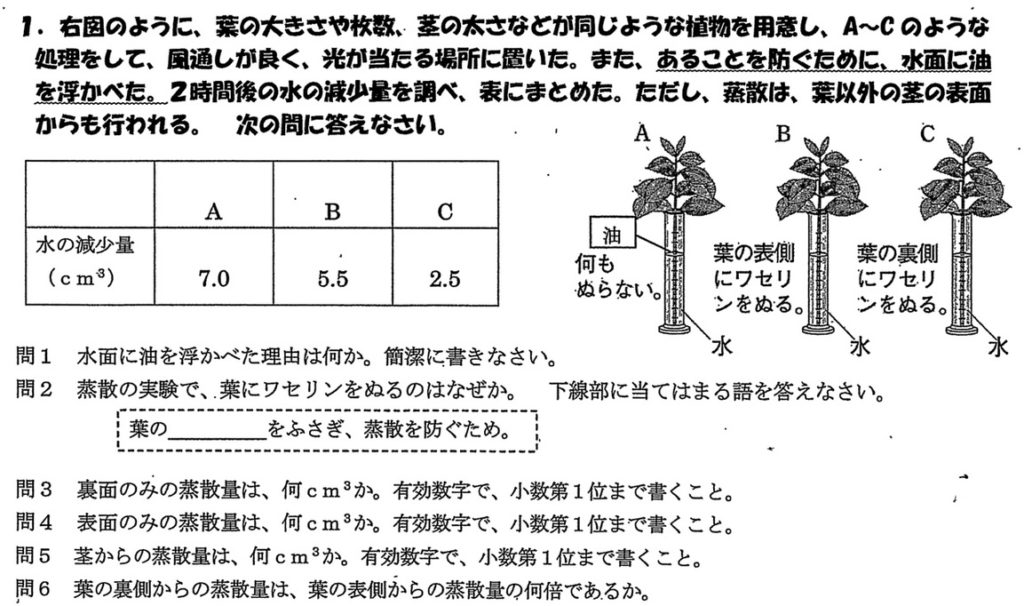
(1)
蒸散量を正確に測定するために、水面に油を浮かべます。
これにより、試験管内の水の蒸発を防ぐことができます。
(2)
葉にワセリンを塗ることで、葉の気孔をふさぎ、蒸散が行われなくなります。
(3)(4)(5)(6)
蒸散量は、
A=葉の表+葉の裏+茎=7.0cm3/2h
B=葉の裏+茎=5.5cm3/2h
C=葉の表+茎=2.5cm3/2h
より、
葉の表=A-B=D=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の裏+茎)=7.0cm3/2h-5.5cm3/2h=1.5cm3/2h
葉の裏=A-C=E=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の表+茎)=7.0cm3/2h-2.5cm3/2h=4.5cm3/2h=3D
茎=A-D-E=(葉の表+葉の裏+茎)-(葉の表)-(葉の裏)=7.0cm3/2h-1.5cm3/2h-4.5cm3/2h=1.0cm3/2h
第2問
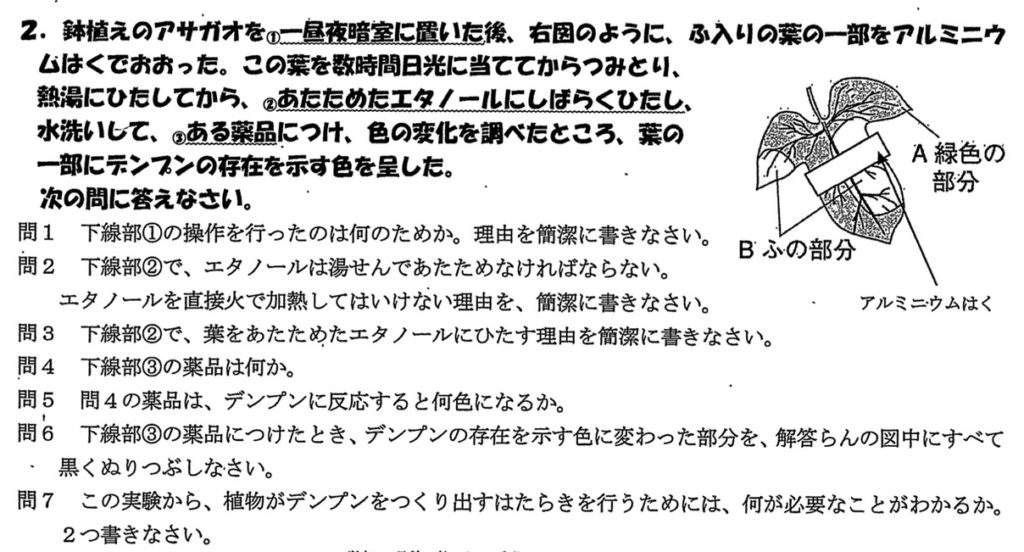
(1)
解答例:葉が呼吸のみ行うことでデンプンがなくなるから(解説略)
(2)
解答例:エタノールは可燃性の物質であるから(解説略)
(3)
解答例:葉の緑色を脱色し、ヨウ素液の色の変化を見やすくするため(解説略)
(4)
答:ヨウ素液(解説略)
(5)
答:青紫色(解説略)
(6)
光合成は植物細胞の細胞質にある葉緑体で行われ、光合成によってグルコース(ブドウ糖)→デンプンが作られます。
葉緑体は、葉の柵状組織、海綿状組織、孔辺細胞にあるので、その部分に色を塗ります。
(7)
光合成の反応式は、以下の通りです。
水(道管より)+二酸化炭素(気孔より)→酸素(気孔から放出)+デンプン(2糖類のスクロース(ショ糖)に分解され師管へ)
スポンサーリンク
第3問
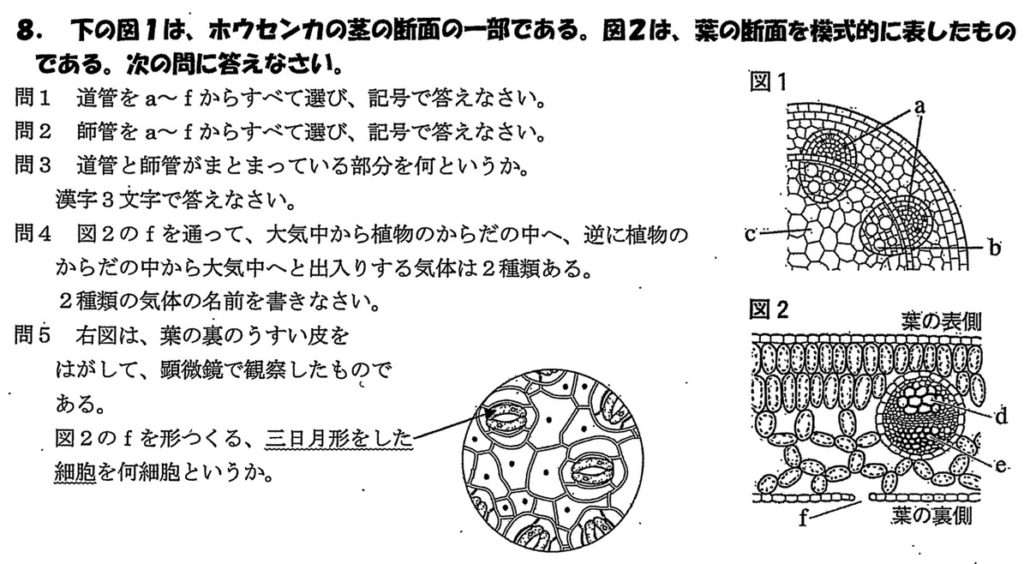
(1)
茎の道管は維管束の内側(b)、葉の道管は維管束(葉脈)の上側(葉の表側)(d)にあります。
(2)
茎の師管は維管束の外側(a)、葉の師管は維管束(葉脈)の下側(葉の裏側)(e)にあります。
(3)
答:維管束(解説略)
(4)
気孔から出入りする気体は、二酸化炭素と酸素です。
光合成では、二酸化炭素が入って酸素が出ます。
呼吸では、酸素が入って二酸化炭素が出ます。
(5)
答:孔辺細胞(解説略)
第4問
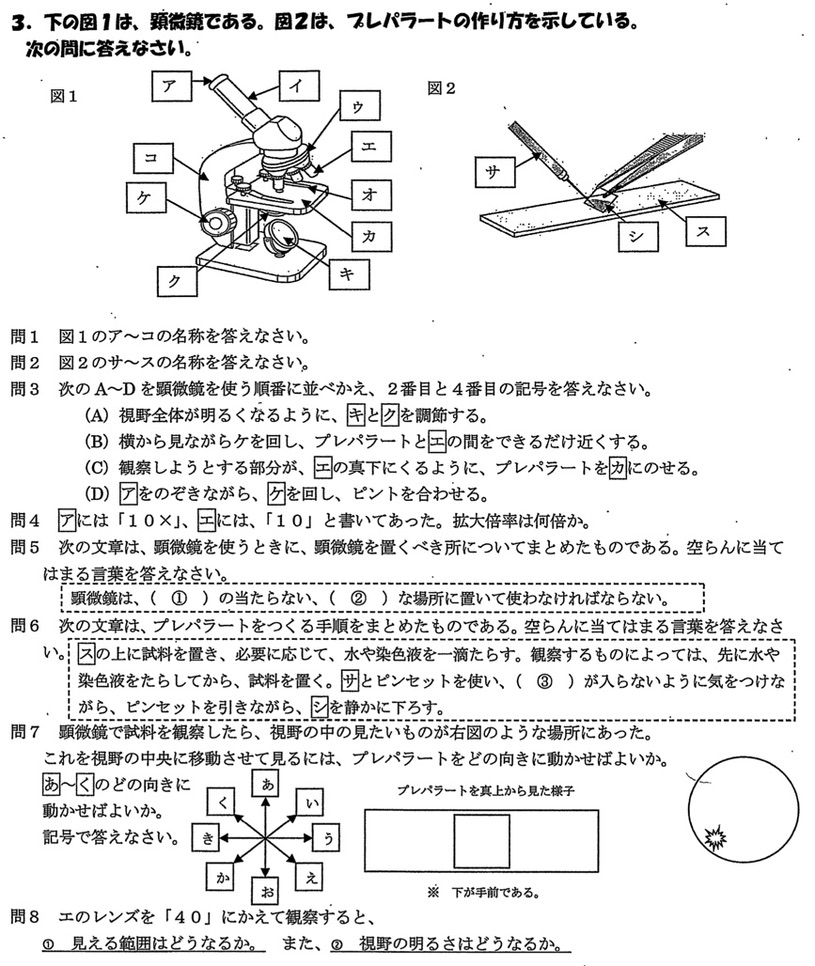
(1)
ア:接眼レンズ、イ:鏡筒、ウ:レボルバー、エ:対物レンズ、オ:クリップ、カ:ステージ、キ:反射鏡、ク:しぼり、ケ:調節ねじ、コ:アーム
※入試ではここまで細かい知識は問われません。
(2)
サ:枝つき針、シ:カバーガラス、ス:スライドガラス
(3)
C→A→B→D
ピントを合わせるとき、近づけてから遠ざけるのがポイントです。
これを軸にして、細かい語句を暗記するとよいでしょう。
(4)
10×10=100倍(解説略)
(5)
顕微鏡は、直射日光の当たらない水平な場所で使用します。
(6)
答:気泡(解説略)
(7)
ステージ上下式顕微鏡では、上下左右逆の倒立像が見えます。
これより、試料を右上に移動させたい場合、プレパラートを左下に動かします。
(8)
対物レンズを10倍から40倍に変更すると倍率が4倍になり、視野と明るさは1/16倍になります。
つまり、視野が狭く、暗くなります。